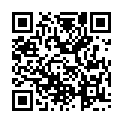聖霊降臨後第11主日
初めの日課 列王記上 19:1-21 【旧約・565頁】
第二の日課 ローマ 11:13-24 【新約・290頁】
福音の日課 マタイ 14:22-33 【新約・28頁】
5000人以上の大群衆の飢えを満たすという奇跡の後、主イエスは弟子たちを湖の向こう岸へ強いて渡らせる。その後、山で一人祈られる主イエス姿は、十字架の直前の出来事を読者である私たちに再び連想させる。一方、弟子たちが沖にこぎ出す様子は、まるでこの世における信仰者の集まりとしての教会の姿を思い起こさせる。命じられたまま沖に漕ぎ出した舟は、進むことも戻ることもできないまま、暗い一夜を過ごさねばならなくなる。彼らのうちには漁師達もいたのであるから、そうした難に際しての経験と知識そして技術を有していたはずである。しかしいまや、彼らはそうした人間的な経験・知識・技術では太刀打ちできない危機の中に陥ってしまう。彼らの人間的な能力や、これまで積み重ねてきたもの、それらは今や全く役に立たない。むしろ、そうしたものがかえって、彼らの恐れと不安そして疑いを増大させることとなった。舟の上での弟子たちの会話について聖書は語らない。しかし、おそらく舟上では、このような事態になったのは誰のせいであるかと互いを非難しあい、誰の言うことが正しいか、どうやって自分だけは助かろうか、と言い争っていたのではないだろうか。舟を揺さぶる波風は、同時に舟の中にある弟子たちの内面をも強く揺さぶる。その危機の中で、弟子たちは水の上を歩く人影が近づいてくるのを目撃し、さらなる恐怖に襲われることとなる。動揺と混乱の極みにある弟子たちに、主イエスは語りかける。「安心しなさい。わたしだ。恐れることはない」。かつて主イエスは嵐を静められた時(8:23-27)、弟子たちは「この方はどういう方なのだろう」と問うだけであった。しかし、十字架への道筋が際立ってくるに至って、弟子たちは目の前におられる方こそが、救い主キリストであることを知る。今や弟子たちは「本当に、あなたは神の子です」とその信仰を告白する。
救い主の呼びかけによって、ペトロもまた湖の上を歩み出す。しかしすぐに風に恐れをなし波に飲み込まれてしまい、すぐに主イエスによってすくい上げられなければならなくなる。波風を前にペトロは、自分の持てる力は何一つ、この事態の中で役に立たないこと、自分はただ主イエスを呼び求めるしかないことを知る。けれどもその危機の中で、主イエスはペトロに最も近くおられることを知ることとなる。そして主イエスは「信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか」とペトロに問いかける。しかし、ここには一つの逆説がある。主イエスは信仰者ではないものに対して、「信仰の薄い者よ」と呼びかけ、問いかけることはされない。その意味で、主イエスのこの問いかけは信仰の不足を咎め立てているのではない。それはむしろ、「安心しなさい。わたしだ。恐れることはない。」という呼びかけと対になって、この世の波風の中を史砕くことなど出来ず、溺れゆくしかない私たちを、すくい上げ力づける言葉なのである。
主イエスは、十字架の死というあらゆる危機のただ中へと決然と歩まれる。それは、私たち一人一人の迎える危機のただ中に、救い主キリストが共におられるためであった。だからこそ私たちが、「主よ、助けて下さい」と叫びを上げるとき、主イエスは私たちの最も近くあって、私たちをすくい上げてくださるのである。
初めの日課 列王記上 19:1-21 【旧約・565頁】
第二の日課 ローマ 11:13-24 【新約・290頁】
福音の日課 マタイ 14:22-33 【新約・28頁】
5000人以上の大群衆の飢えを満たすという奇跡の後、主イエスは弟子たちを湖の向こう岸へ強いて渡らせる。その後、山で一人祈られる主イエス姿は、十字架の直前の出来事を読者である私たちに再び連想させる。一方、弟子たちが沖にこぎ出す様子は、まるでこの世における信仰者の集まりとしての教会の姿を思い起こさせる。命じられたまま沖に漕ぎ出した舟は、進むことも戻ることもできないまま、暗い一夜を過ごさねばならなくなる。彼らのうちには漁師達もいたのであるから、そうした難に際しての経験と知識そして技術を有していたはずである。しかしいまや、彼らはそうした人間的な経験・知識・技術では太刀打ちできない危機の中に陥ってしまう。彼らの人間的な能力や、これまで積み重ねてきたもの、それらは今や全く役に立たない。むしろ、そうしたものがかえって、彼らの恐れと不安そして疑いを増大させることとなった。舟の上での弟子たちの会話について聖書は語らない。しかし、おそらく舟上では、このような事態になったのは誰のせいであるかと互いを非難しあい、誰の言うことが正しいか、どうやって自分だけは助かろうか、と言い争っていたのではないだろうか。舟を揺さぶる波風は、同時に舟の中にある弟子たちの内面をも強く揺さぶる。その危機の中で、弟子たちは水の上を歩く人影が近づいてくるのを目撃し、さらなる恐怖に襲われることとなる。動揺と混乱の極みにある弟子たちに、主イエスは語りかける。「安心しなさい。わたしだ。恐れることはない」。かつて主イエスは嵐を静められた時(8:23-27)、弟子たちは「この方はどういう方なのだろう」と問うだけであった。しかし、十字架への道筋が際立ってくるに至って、弟子たちは目の前におられる方こそが、救い主キリストであることを知る。今や弟子たちは「本当に、あなたは神の子です」とその信仰を告白する。
救い主の呼びかけによって、ペトロもまた湖の上を歩み出す。しかしすぐに風に恐れをなし波に飲み込まれてしまい、すぐに主イエスによってすくい上げられなければならなくなる。波風を前にペトロは、自分の持てる力は何一つ、この事態の中で役に立たないこと、自分はただ主イエスを呼び求めるしかないことを知る。けれどもその危機の中で、主イエスはペトロに最も近くおられることを知ることとなる。そして主イエスは「信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか」とペトロに問いかける。しかし、ここには一つの逆説がある。主イエスは信仰者ではないものに対して、「信仰の薄い者よ」と呼びかけ、問いかけることはされない。その意味で、主イエスのこの問いかけは信仰の不足を咎め立てているのではない。それはむしろ、「安心しなさい。わたしだ。恐れることはない。」という呼びかけと対になって、この世の波風の中を史砕くことなど出来ず、溺れゆくしかない私たちを、すくい上げ力づける言葉なのである。
主イエスは、十字架の死というあらゆる危機のただ中へと決然と歩まれる。それは、私たち一人一人の迎える危機のただ中に、救い主キリストが共におられるためであった。だからこそ私たちが、「主よ、助けて下さい」と叫びを上げるとき、主イエスは私たちの最も近くあって、私たちをすくい上げてくださるのである。