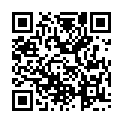復活後第2主日
初めの日課 使徒言行録 4:5-12 【新約・219頁】
第二の日課 1ヨハネ 1:1-2:2 【新約・441頁】
福音の日課 ヨハネ福 21:1-14 【新約・211頁】
伝統的なキリスト教の暦では復活祭後第2主日には、詩編33編5節「地は主の慈しみに満ちている」からとられた“Miserikordias Domini”(ミセリコルディアス ドミニ「主の憐み」)という名前が付けられている。この名は、主イエスが死から復活されたことは主なる神の慈しみと憐みがこの地に満ち溢れる出来事であるということ、そしてそれは私たちにとっての永遠の喜びであるという、古代の教会の信仰告白を現代の私たちに伝えている。
十字架の出来事によって、主イエスが弟子たちの元から失われた後、弟子たちは漁に出掛ける。それは彼らの多くにとっては、もともと慣れ親しんだ職業であった。主イエス亡き今、彼らは、主イエスに出会う以前の生活に戻ろうとしている。しかし、慣れ親しんだはずの漁は、決して実り豊かなものではなかった。彼らは空しいまま、夜明けを迎える。その時、甦られた主イエスは岸辺で弟子たちを待っていた。しかし空しいまま時を過ごす弟子たちには、それが主イエスであることが分からなかった。その男は語る。「船の右側に網を打ちなさい。そうすればとれるはずだ」。そして弟子たちが命じられたとおり網を打つと、「魚があまりにも多くて、もはや網を引き上げることができなかった」。一晩空しいまま繰り返してきた作業は、この男の言葉によって、大いなる実りへと変えられる。その時はじめて、弟子たちは、それが主イエスに他ならないことがわかるのであった。彼らは漁を終えて、主イエスが整えられた食卓を囲む。その時「弟子たちはだれも、『あなたはどなたですか』と問いただそうとはしなかった。主であることをしっていたからである」。
私たちは、時として人生の中で、生きる意味を見失い、空しく、何の実りも得ることもできないまま時を過ごさねばならない時がある。しかし、そのような時に甦りの主が私たちのもとを訪れられることを、本日の聖書は語る。さらに、主イエスがともにおられる時、そして私たちが主イエスの言葉に聴き従う時、私たちの成す空しい技は実り豊かなものへと変えられることを、聖書は語る。復活の主が私たちに与えられたということ、それは、私たちの目には、失敗と挫折、喪失と敗北としか映らない出来事のその先にこそ、新しい永遠の命が始まっていることを、神が私たちに示されたということに他ならない。私たち人間が「復活の主を知る」とは、それは、自分には失われてしまったと思いこんでいた、生の意味、命の意味を、再び知ることであり、主イエスとの出会いを通して私たちの空しい技が実りへと変えられるということなのである。それはまさに主の憐れみと慈しみに満たされる出来事である。

初めの日課 使徒言行録 4:5-12 【新約・219頁】
第二の日課 1ヨハネ 1:1-2:2 【新約・441頁】
福音の日課 ヨハネ福 21:1-14 【新約・211頁】
伝統的なキリスト教の暦では復活祭後第2主日には、詩編33編5節「地は主の慈しみに満ちている」からとられた“Miserikordias Domini”(ミセリコルディアス ドミニ「主の憐み」)という名前が付けられている。この名は、主イエスが死から復活されたことは主なる神の慈しみと憐みがこの地に満ち溢れる出来事であるということ、そしてそれは私たちにとっての永遠の喜びであるという、古代の教会の信仰告白を現代の私たちに伝えている。
十字架の出来事によって、主イエスが弟子たちの元から失われた後、弟子たちは漁に出掛ける。それは彼らの多くにとっては、もともと慣れ親しんだ職業であった。主イエス亡き今、彼らは、主イエスに出会う以前の生活に戻ろうとしている。しかし、慣れ親しんだはずの漁は、決して実り豊かなものではなかった。彼らは空しいまま、夜明けを迎える。その時、甦られた主イエスは岸辺で弟子たちを待っていた。しかし空しいまま時を過ごす弟子たちには、それが主イエスであることが分からなかった。その男は語る。「船の右側に網を打ちなさい。そうすればとれるはずだ」。そして弟子たちが命じられたとおり網を打つと、「魚があまりにも多くて、もはや網を引き上げることができなかった」。一晩空しいまま繰り返してきた作業は、この男の言葉によって、大いなる実りへと変えられる。その時はじめて、弟子たちは、それが主イエスに他ならないことがわかるのであった。彼らは漁を終えて、主イエスが整えられた食卓を囲む。その時「弟子たちはだれも、『あなたはどなたですか』と問いただそうとはしなかった。主であることをしっていたからである」。
私たちは、時として人生の中で、生きる意味を見失い、空しく、何の実りも得ることもできないまま時を過ごさねばならない時がある。しかし、そのような時に甦りの主が私たちのもとを訪れられることを、本日の聖書は語る。さらに、主イエスがともにおられる時、そして私たちが主イエスの言葉に聴き従う時、私たちの成す空しい技は実り豊かなものへと変えられることを、聖書は語る。復活の主が私たちに与えられたということ、それは、私たちの目には、失敗と挫折、喪失と敗北としか映らない出来事のその先にこそ、新しい永遠の命が始まっていることを、神が私たちに示されたということに他ならない。私たち人間が「復活の主を知る」とは、それは、自分には失われてしまったと思いこんでいた、生の意味、命の意味を、再び知ることであり、主イエスとの出会いを通して私たちの空しい技が実りへと変えられるということなのである。それはまさに主の憐れみと慈しみに満たされる出来事である。